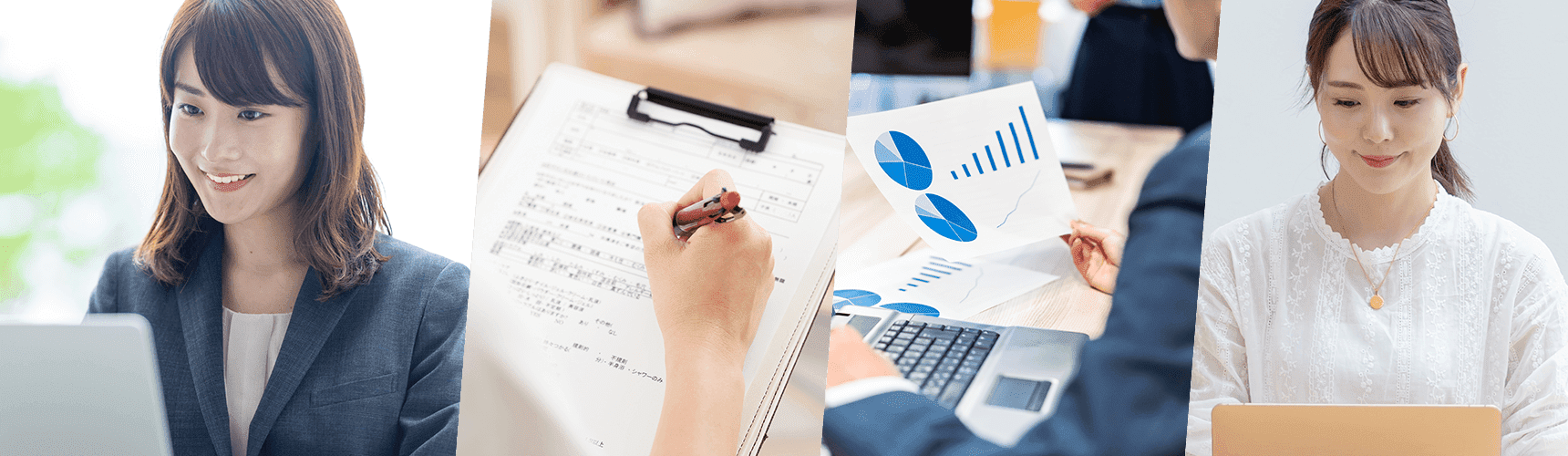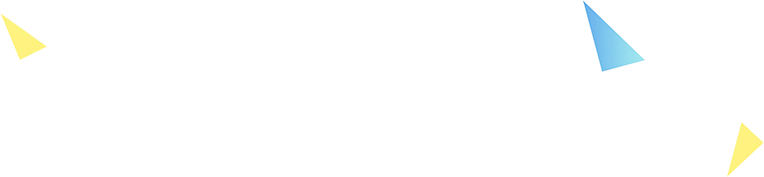自治体で広がる「カスハラ防止条例」──企業がいま押さえるべきポイントと実践対策
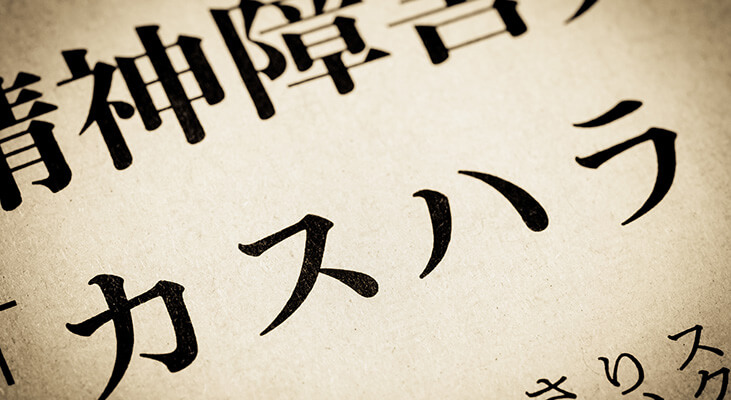
2025年4月1日、東京都・群馬県・北海道で「カスタマーハラスメント防止条例」が全国で初めて施行されました。2022年に厚生労働省が公表した「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」では努力義務にとどまっていましたが、2026年度からはすべての企業で対策が義務化されます。そのため、今こそ企業は計画的かつ具体的に対応を進めていく必要があります。
今回は、カスタマーハラスメント(以下、カスハラ)防止に関する条例のポイントや、義務化を踏まえた実践的なカスハラ対策の方法について解説します。
カスハラとは?
カスハラとは、カスタマーハラスメントの略称で、顧客などからの、従業員に対する著しい迷惑行為を指し、従業員の就業環境を阻害するものです。具体的な行為としては、暴行、脅迫、その他の違法な行為、正当な理由のない過度な要求や暴言などの不当な行為が挙げられます。
厚生労働省の定義によれば、「職場において行われる顧客、取引の相手方、施設の利用者その他の当該事業主の行う事業に関係を有する者の言動であって、その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより当該労働者の就業環境を害すること」とされています。
つまり、次の3つの要件を満たす場合に「カスハラ」と定義されます。
1.顧客、取引先、施設利用者その他の利害関係者が行う、
2.社会通念上許容される範囲を超えた言動により、
3.労働者の就業環境を害すること。
【出典】
【関連コラム】
●2025年労働施策総合推進法改正により対策義務化
2025年6月11日に、厚生労働省より「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律」が公布されました。
カスハラ対策の義務化は「事業主」と広く定義されているため、企業の経営者はカスハラ対策を実施する必要があります。
カスハラ防止条例が自治体で広がる
2025年4月に自治体によりカスハラ防止条例が施行されましたが、これらは自治体の区域内に所在し、事業を営む法人・団体・個人が対象となるものです。
条例が施行された地域の事業主は、地域問わず義務化される2026年度に備える意味でも、対応を急ぐ必要があります。
おすすめ
- ・カスハラで従業員が疲弊している
- ・クレームとカスハラの区別が難しい
- ・カスハラの研修内容が気になる

カスハラ防止条例の例
2025年4月1日に施行された自治体によるカスハラ防止条例の例として次の3つが挙げられます。
東京都カスタマー・ハラスメント防止条例(2024年10月11日公布)
事業を行う都内の法人、その他の団体、個人を対象とするものです。
カスハラは、顧客などによる著しい迷惑行為が、就業者の人格または尊厳を侵害するなど就業環境を害し、事業者の事業の継続に影響を及ぼすものであるとの認識の下、社会全体でその防止が図られなければならないとしています。防止に当たっては、顧客などと就業者とが対等の立場において相互に尊重することが示されています。
東京都が示す「事業者の6つの取り組み」
1. 社内外への基本方針・姿勢の明確化と周知
2. 相談窓口の設置と体制の整備
3. 被害防止のマニュアル整備
4. 被害を受けた者への配慮
5. 就業者への教育研修
6. 定期的な見直しや対策の継続
【出典】
事業者に対する罰則の規定はありません。
北海道カスタマーハラスメント防止条例(2024年11月29日公布)
東京都と同様、事業を行う北海道内の法人、その他の団体、個人を対象とするものです。
事業者はカスハラ防止策を主体的に行うことが示されています。
「北海道カスタマーハラスメント対策チェックシート(事業者版)」によれば、事業者は、下記の取り組みを実施する必要があります。
1.カスタマーハラスメントの相談対応者や相談窓口を決めている。
2.相談対応者や相談窓口について、従業者に周知している。
3.社内でのカスタマーハラスメントに該当する行為、判断基準を明確化している。
4.カスタマーハラスメントへの対応マニュアルを作成している。
5.カスタマーハラスメントへの対応方針を社内外に発信している。
6.社内対応ルールの従業者への教育・研修を行っている。
7.発生したカスタマーハラスメントについて事実関係を正確に確認し、対応方法を検討している。
8.顧客対応で被害を受けた従業者の安全確保、精神面の配慮を行っている。
9.発生したカスタマーハラスメントの内容を社内で共有し、再発防止の検討を行っている。
10.関係機関への相談対応の検討を行い、連絡先等は相談対応者に周知されている。
事業者に対する罰則の規定はありません。
群馬県カスタマーハラスメント防止条例(2025年3月27日公布)
東京都、北海道同様に、群馬県内の事業を行う法人、その他の団体、個人を対象とするものです。
「第7条 事業者の責務」においては、事業者は顧客への啓発、就業者への研修などを実施し、カスハラ防止策に主体的かつ積極的に取り組むこと、また就業者がカスハラを受けた際に、就業者の安全確保と顧客への中止の申し入れなどの適切な措置を講じることが示されています。
また、事業者の努力義務として下記が挙げられています。
・啓発事業や社内研修を実施し、県等が作成した広報物の掲示等を行う。
・研修等で、顧客側の正しい意見の伝え方を学ぶ機会をつくる。
・就業者がカスタマーハラスメントを受けた際は、場所を移し複数人で対応するなど組織的に対応する。
・必要に応じて顧客等に退店を求める、警察へ通報するなどの対処を行う。
事業者に対する罰則の規定はありません。
企業が実践すべき対策のポイント
各自治体の条例をもとに、企業が実践すべき対策のポイントをまとめると次のことが挙げられます。
基本指針・基本姿勢の明確化と周知
社内外に自社のカスハラに対する基本指針や姿勢を明確に示し、周知徹底します。
相談窓口の設置と体制の整備
従業員がカスハラを受けた際に、気軽に相談できる体制作りと、相談対応のフローなどを整えておく必要があります。
【関連コラム】
カスハラ対応マニュアルの整備
実際にカスハラが発生した際、一般従業員と管理者が迅速かつ適切な対応ができるよう、あらかじめマニュアルを整備しておく必要があります。
【関連コラム】
従業員への教育・研修の実施
自社の指針に基づき、カスハラを受けた際に、具体的な実践方法をケーススタディで示すなど、教育や研修が欠かせません。同時にカスハラ問題の深刻さやリスク、企業としての考え方なども理解を浸透させる必要があります。
【関連コラム】
カスハラを受けた従業員への配慮のための取り組み
カスハラを受けた従業員に対しては、心身共に配慮をすることが重要です。健康に関する訴えがあった場合は適切な対処を講じるなど、対応方法を決めておくことも必要です。
厚生労働省より、具体的な対応方法が提示された際には、その最新情報を参照の上、対応してください。
まとめ
カスハラ対策の義務化を受け、どの企業も対応が求められています。
カスハラ研修・教育に関するリソースや知識、ノウハウ不足でお困りの際には、日本トータルテレマーケティングのカスハラ研修をご検討ください。
 こちらのコラムを読んだあなたへ
こちらのコラムを読んだあなたへ日本トータルテレマーケティングの
カスタマーハラスメント
研修資料
こんな方におすすめ
- ・カスハラで従業員が疲弊している
- ・クレームとカスハラの区別が難しい
- ・カスハラの研修内容が気になる

DL資料無料配布中!