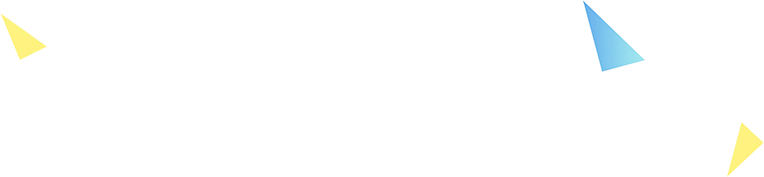カスタマーハラスメント対応フロー|発生に備えて必要な対応も解説

近年、ニュースでもよく耳にするようになったカスタマーハラスメント(カスハラ)。
コールセンターや問い合わせ対応部門では、発生した時とその前に適切な対応をすることが求められています。
本コラムでは、カスハラの定義や基礎、クレームとの違いなどをおさえた上で、実際に対応をする際、どんなポイントに注意して対応すべきか、具体的な対応フロー、そして発生に備えるための対応について解説していきます。
目次
カスタマーハラスメントとは?
カスタマーハラスメント(カスハラ)は、近年、企業の労働環境においての課題として注目されています。以下にて詳しく解説していきます。
カスタマーハラスメントの定義
厚生労働省が提供する「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」によれば、カスハラとは、顧客からのクレームや言動の中で、その要求が社会通念上不相当な手段や態様で行われ、結果として労働者の就業環境を害するものを指します。これは、単なる不満の表明や正当な苦情とは異なり、労働者に対する不当なプレッシャーやストレスを生む行為です。
【関連コラム】
カスタマーハラスメントとクレームの違いとは?
クレームには「正当なクレーム」と「不当なクレーム」が存在します。正当なクレームは、商品の欠陥やサービスの不備に対する合理的な指摘であり、企業にとって改善のための貴重なフィードバックとなります。一方で、不当なクレームは、根拠が薄弱であることや、過度な要求を伴うものであり、これがカスハラに該当します。例えば、無理な要求を繰り返す、または不適切な言葉遣いで従業員を威圧する行為は、不当なクレームに分類される可能性があります。
企業は、正当なクレームと不当なクレームを明確に区別し、適切に対応することが求められます。
カスタマーハラスメントにあたる違法行為
カスタマーハラスメントが行き過ぎる場合、法律に抵触する場合があります。具体的な例としては、以下のような犯罪が該当します。
1.脅迫罪
言葉や態度で相手を恐怖に陥れる言動をする行為。
例えば、「お前の家族に危害を加えるぞ」といった発言が該当します。
2.恐喝罪
相手を恐怖させて金品を不当に要求する行為。
「慰謝料を払わないとネットで悪評を広める」といった行為がこれに該当します。
3.強要罪
暴力や脅迫を用いて相手に義務のないことを行わせる行為。
「謝罪だけでなく、謝罪文を書け」といった要求が該当します。
4.威力業務妨害罪
業務を妨害する目的で威力を行使する行為。
店舗やオフィスに押しかけて業務を中断させる行為などがこれにあたります。
5.不退去罪
正当な理由なくその場を離れない行為。
閉店後も居座り続ける行為がこの罪に該当します。
これらの違法行為は、顧客と企業の関係を損なうだけでなく、従業員の心身に深刻な影響を及ぼす可能性があります。企業は、カスハラに対する適切な対策を講じ、労働者の保護を図ることが求められています。
カスタマーハラスメントが発生した時の対応フロー
カスタマーハラスメントは適切な対応をすることで、従業員の安全を確保し、企業の信用を守ることができます。以下に、具体的な対応フローを紹介します。
1.一人で対応をしない・判断しない
カスタマーハラスメントが発生した場合、まず重要なのは一人で対応をしないことです。状況を上司や同僚に共有し、適切なサポートを受けることが必要です。これにより、冷静かつ客観的な判断が可能になります。また、複数人での対応は、後のトラブルを避けるための証拠としても役立ちます。
2.書類の署名や捺印をしない
ハラスメントを受けた際に、顧客からの書類への署名や捺印を求められることがあるかもしれません。しかし、これに応じることは避けるべきです。署名や捺印は法的な拘束力を持つ可能性があるため、慎重な判断が求められます。会社の指針に従い、必要であれば法務部門に相談することが重要です。
3.解決を急がない
問題解決を急ぐあまり、不適切な対応をしてしまうことは避けましょう。カスタマーハラスメントは感情的な問題が絡むことが多く、冷静な対応が求められます。時間をかけて状況を分析し、最適な解決策を見つけることが重要です。
4.警察に連絡する
状況がエスカレートし、従業員の安全が脅かされる場合は、警察に連絡することも視野に入れるべきです。企業としては、従業員の安全を最優先に考え、必要な措置を講じることが求められます。警察との連携は、問題の迅速な解決につながる可能性があります。
おすすめ
- ・カスハラで従業員が疲弊している
- ・クレームとカスハラの区別が難しい
- ・カスハラの研修内容が気になる

カスタマーハラスメントに備えて必要な対応
カスタマーハラスメントは発生した時の対応だけでなく、発生する前に対応を講じることも重要です。ここでは、カスタマーハラスメントに備えて、どんな対応ができるか整理して解説します。
カスタマーハラスメント対応マニュアルを作成する
まずは、自社の業務に応じたカスタマーハラスメント対応マニュアルの作成が重要です。厚生労働省が提供する「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」などを参考にし、具体的な対応策を明文化することで、スタッフが安心して業務に取り組むことができます。
詳細については以下の記事をご参照ください。
【関連コラム】
商品契約時の説明
商品契約時の説明も重要になります。顧客に対して、契約内容やサービスの範囲を明確に伝えることで、誤解や不満を未然に防ぐことができます。
ホームページやポスターなどで周知する
ホームページやポスターなどを活用して、カスタマーハラスメントに関する情報を広く周知することも効果的です。これにより、顧客に対して企業の方針を理解してもらい、ハラスメント行為を抑止する効果が期待できます。
カスタマーハラスメントと正当なクレームを区別できる仕組みづくり
カスタマーハラスメントと正当なクレームを区別できる仕組みづくりも必要です。これには、クレーム内容を分析し、正当な要求と不当な要求を判断するための基準を設けることが含まれます。この基準に基づいて、従業員が適切に対応できるようにすることで、無用なストレスを軽減することができます。
【関連サービス】
【関連リンク】
【関連コラム】
カスタマーハラスメントへの相談体制を明確にする
カスタマーハラスメントへの相談体制を明確にすることも重要です。従業員が困った際にすぐに相談できる窓口を設置し、迅速に問題解決が図れるようにすることで、安心して業務に取り組むことができる環境を整えることができます。
コールセンターの役割は外部のサービスを活用する
外部のサービスを活用することも一案です。コールセンターをアウトソースする事で、カスハラ対応の負担を軽減し、より効率的な業務運営が可能となります。外部の専門家による対応は、従業員のストレスを軽減し、企業全体の生産性向上にも寄与します。
経験豊富な講師と実績。オーダーメイドのカスハラ研修なら日本トータルテレマーケティングへ
この記事では、カスタマーハラスメントとは何かの解説から、発生した際の対応や発生に備えた対応などをご紹介しました。
カスタマーハラスメントへの対応では、方法や手順の策定だけでなく、研修を実施することも重要です。その際、カスタマーハラスメントの対応を専門とする業者に研修依頼をすることで、職員はハラスメントの理解を深め、実践的な対応スキルを身につけることや社内のナレッジ蓄積にもなります。
日本トータルテレマーケティング株式会社は、さまざまな業界のBPOサービスを支援しているだけでなく、オペレーターへのカスタマーハラスメント対応研修を提供しています。
クレームとハラスメントの見極め方や組織としての対応の在り方、上席者の対応訓練などを行い、冷静に毅然と対応できるスキルをオーダーメイドで企画いたします。
詳細は以下サービスページをご覧ください。
 こちらのコラムを読んだあなたへ
こちらのコラムを読んだあなたへ日本トータルテレマーケティングの
カスタマーハラスメント
研修資料
こんな方におすすめ
- ・カスハラで従業員が疲弊している
- ・クレームとカスハラの区別が難しい
- ・カスハラの研修内容が気になる

DL資料無料配布中!