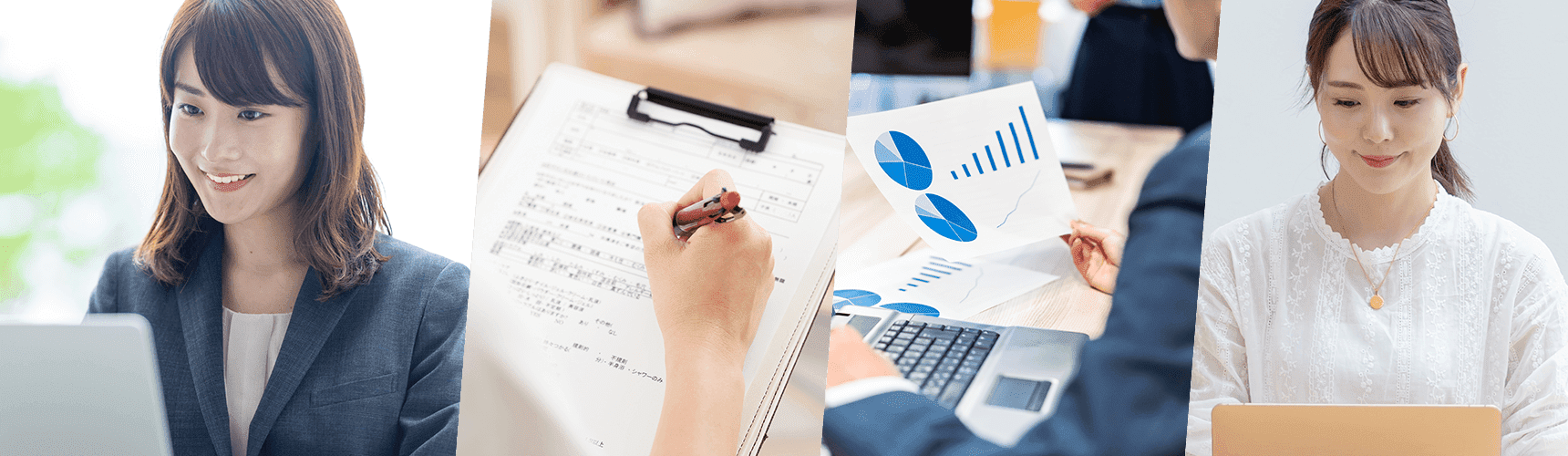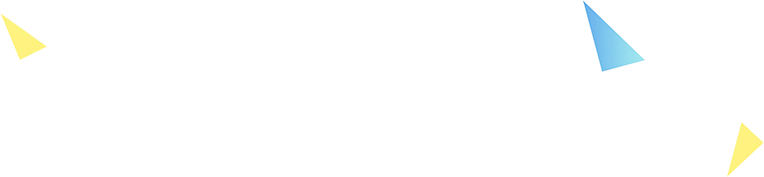カスハラ事例で読み解くリスクマネジメント~社員・従業員を守るポイント~

近年、ハラスメント被害は深刻化しており、国全体でハラスメント防止に向けた対策が強化されています。その中でも、カスタマーハラスメント(以下、カスハラ)は深刻な社会問題の一つとして注目されており、企業に対しても対策を講じることが義務付けられつつあります。
今回は、企業が今後どのようにリスクマネジメントを進めるべきか、そのポイントを探るために、カスハラの具体的な事例をご紹介します。カスハラ対策のヒントにぜひお役立てください。
カスハラとは?
カスハラとは、カスタマーハラスメント(以下、カスハラ)の略称です。従業員に対する顧客等からの著しい迷惑行為を指し、従業員の就業環境を阻害するものです。具体的な行為としては、暴行、脅迫、違法行為のほか、正当な理由のない過度な要求や暴言などです。
厚生労働省の定義によれば、「職場において行われる顧客、取引の相手方、施設の利用者その他の当該事業主の行う事業に関係を有する者の言動であって、その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより当該労働者の就業環境を害すること」とされています。
つまり、次の3つの要件を満たす場合に「カスハラ」と定義されます。
1.顧客、取引先、施設利用者その他の利害関係者が行う、
2.社会通念上許容される範囲を超えた言動により、
3.労働者の就業環境を害すること。
【出典】
【関連コラム】
カスハラの具体的な行為類型
カスハラの具体的な行為類型として、東京都は次のように定義しています。
類型1:要求内容が妥当性を欠く
顧客に提供する商品・サービスに瑕疵や過失が認められないケースや、顧客からの要求内容が、従業員が提供する商品・サービスの内容とは関係がないなど、要求に妥当性を欠く場合です。
類型2:顧客等の要求内容の妥当性にかかわらず、要求を実現するための手段・態様が違法又は社会通念上不相当である
顧客からの要求が妥当であるかどうかにかかわらず、違法又は社会通念上、不当なものです。例えば、身体的・精神的な攻撃、威圧的な言動、土下座の要求、執拗な言動等が挙げられます。
類型3:顧客等の要求内容の妥当性に照らして、要求を実現するための手段・態様が違法又は社会通念上不相当である
顧客からの要求の妥当性に照らして、実現するための手段や態度等が違法、または社会通念上、不当なものです。例えば、過度な商品交換や金銭補償、謝罪の要求等が挙げられます。
おすすめ
- ・カスハラで従業員が疲弊している
- ・クレームとカスハラの区別が難しい
- ・カスハラの研修内容が気になる

カスハラ対策の必要性
顧客対応を行う企業は、従業員に対するカスハラを予防し、もしカスハラを受けた場合は適切な対策を講じる必要があります。ここでは、企業がカスハラ対策を進めるべき理由を整理します。
カスハラ対策が義務化
2024年10月4日に制定された「東京都・カスタマー・ハラスメント防止条例」の他、いくつかの自治体でカスハラ条例が施行されていますが、それ以外は法的な規制はありませんでした。そのため日本全国の企業がカスハラ対策を実施する義務はありません。
しかし、2025年6月11日に「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律」が公布されました。
この改正を受け、カスハラ防止措置が事業主の義務となり、施行は公布の日から起算して1年6ヶ月以内に政令で定める日とされ、2026年度中の施行が予定されています。
厚生労働省の資料によれば、事業主が行うべき具体的な措置の内容は、今後、指針によって示されますが、主に次のことが挙げられています。
・事業主の方針等の明確化およびその周知・啓発
・相談体制の整備・周知
・発生後の迅速かつ適切な対応・抑止のための措置
方針の策定や社内周知、相談体制、発生後の対応体制整備等を早期から進めておくことが重要です。
日本で起きた深刻なカスハラ事例2選
カスハラはすでに日本で多発していますが、その中でも、どのようなカスハラが起きているのか確認しておきましょう。
飲食店の事例
ある飲食店では、当時20代の男性社員が、顧客からの通信販売の注文や商品に関する問い合わせ、クレームなどの電話対応を担当していました。電話口では「死ね」「バカ」「もっと客の立場になれ」などと暴言が繰り返され、不当要求も長期化しました。そのような顧客からの対応を受けてか、男性社員はうつ病を発症し、自死に至りました。
その後、男性社員の母親が心理的負荷による精神障害の労災認定を申請しましたが、労災は認められませんでした。
男性社員が残した業務日報には暴言や理不尽な要求について明確に記録されていましたが、通信販売受付の電話機には内線機能のほか、電話番号を表示するナンバーディスプレイや、録音機能がついておらず、孤立していたとみられています。
教育委員会職員の事例
ある都市の教育委員会では、公立小学校における職員間いじめの問い合わせや苦情電話などに対応していた当時30代の男性係長がいました。その心理的負荷に加え、長時間労働が重なり、精神疾患を発症し自死に至りました。
実際、残業時間は月90時間と多く、上司には睡眠薬を服用している旨を伝えていました。男性の遺族が都市の責任を追及して裁判を起こした結果、都市側が健康管理義務を怠ったとして賠償責任が認定されました。
事例から読み解くカスハラのリスクマネジメントのポイント
事例を受け、企業はどのようなリスクマネジメントを進めるべきか、ポイントをご紹介します。
カスハラ対策は義務であることの理解
事例では、カスハラ対策が義務化される前であったこともあり、カスハラ対策を怠ったことに責任が追及されました。すでに東京都のカスハラ条例では義務化されましたが、今後、全国的に義務化されるに当たって、まずはカスハラ対策に真摯に取り組むことが重要です。社内への周知徹底を行い、組織的に対応策を進める必要があります。
被害者への配慮
事例では、クレーム電話などを一人で対応させ続けていたことが大きな問題に発展していました。今後は、カスハラと思われる行為を受けた場合に、一人で対応させないこと、そしてあらかじめ定めた組織的な対応策を規定通りに実践することが求められます。
被害者のための相談体制の整備
カスハラを受けていることを社内に隠す、または言い出せない従業員についての配慮も求められます。カスハラ被害を受けていると思ったら、すぐに相談できる社内の体制づくりが欠かせません。
【関連コラム】
カスハラ行為の記録・分析
飲食店の事例では、電話の通話録音機能がついていなかったため、会話の内容の分析もできない状況でした。今後は、トラブル防止や問題が発生したときの証拠にもなる通話録音機能はより一層、重要になってくるでしょう。
まとめ
カスハラ対策の義務化が目前に迫る中、社内の全従業員がカスハラ対策の重要性を正しく認識し、実践につながる具体的な取り組みを早急に進める必要があります。
ご紹介した事例のような事態が発生することを徹底的に防ぐためにも、早めの準備を進めましょう。
日本トータルテレマーケティングでは、カスハラ研修を実施しております。
詳細はお気軽にお問い合わせください。
 こちらのコラムを読んだあなたへ
こちらのコラムを読んだあなたへ日本トータルテレマーケティングの
カスタマーハラスメント
研修資料
こんな方におすすめ
- ・カスハラで従業員が疲弊している
- ・クレームとカスハラの区別が難しい
- ・カスハラの研修内容が気になる

DL資料無料配布中!