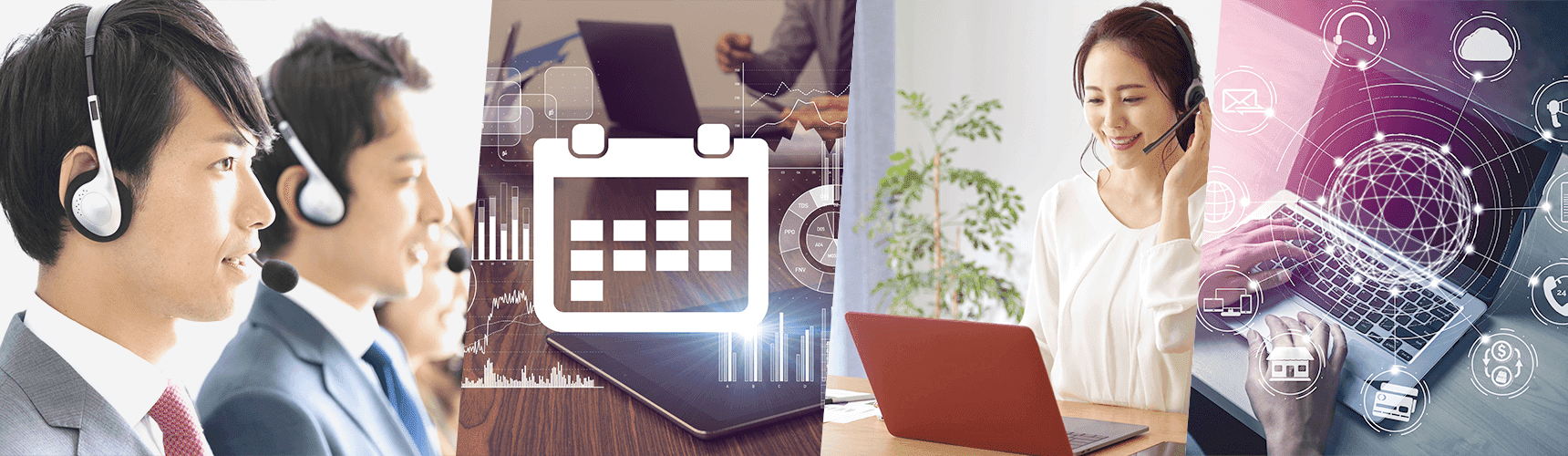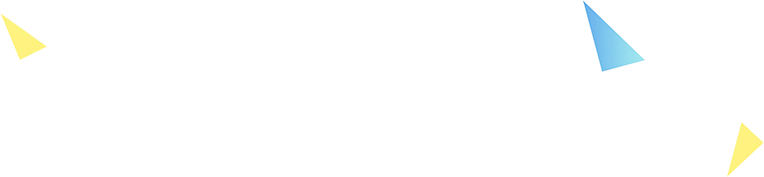コールセンターの稼働率とは?
応答率、占有率と合わせた生産性向上のポイント

コールセンターは人手不足による業務効率化やCX(顧客体験価値)向上など、さまざまな課題に直面しています。そのような中、生産性を向上させるために適切なKPIを指標として設定し、測定・改善を重ねることが求められています。
今回は、コールセンターの稼働率とは何か、また応答率や占有率との違い、コールセンターの稼働率の課題、稼働率を適正にするポイントについて解説します。
コールセンターの稼働率とは?
コールセンターの稼働率の概要と管理が重要な理由を解説します。
コールセンターの稼働率とは?
コールセンターにおける稼働率とは、オペレーターが勤務している時間のうち、実際に顧客対応に費やしている時間の割合を指します。これは単に電話に出ている時間だけでなく、顧客対応に関わるすべての活動時間を含みます。具体的には、顧客との通話時間、通話内容を記録するなどの後処理時間、顧客を待たせる保留時間、そして次の入電を待つ待機時間などが含まれます。
この稼働率は、コールセンターの健全な運営や適切な人員配置を判断する上で非常に重要な指標です。
稼働率を把握することで、コールセンターが効率的に運営されているか、人員に過不足がないか、そしてオペレーターが過度なストレスを抱えていないかといった、さまざまな課題に気づくことができます。
この指標を最適に保つことが、生産性向上とコスト削減の両立につながります。
【稼働率の計算式】
稼働率は次の計算式で算出できます。
顧客応対時間÷勤務時間×100=稼働率(%)
例えば8時間勤務のオペレーターの対応時間が6.5時間であった場合、
6.5÷8×100=81.25%
となり、およそ81%の稼働率であることがわかります。
コールセンターの稼働率管理が重要な理由
稼働率は、コールセンターを管理する指標の一つですが、コールセンターの健全な運営や適切な人員調整のために重要な指標です。
稼働率を管理することは、コールセンターが生産性を確保できているかを知ることができるとともに、オペレーターの心身の不調やストレスの度合い、余剰人員による無駄なコストなどに気づくことができます。
稼働率は最適なリソースで効果最大化を図るために重要な指標といえるのです。
おすすめ
- ・コールセンターサービスについて知りたい
- ・コールセンターの成功事例を知りたい
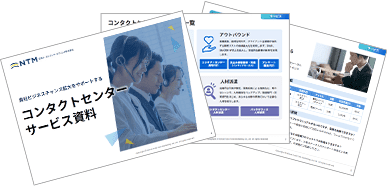
コールセンターの稼働率と応答率、占有率との違い
コールセンターには、稼働率のほか、応答率、占有率といった指標もあります。それぞれの違いを解説します。
応答率とは?
応答率とは、コールセンターにかかってくる電話の着信件数に対して、どれくらいの件数を応答できたかを示す割合です。お客様にとっては「つながりやすさ」を意味します。
オペレーターの対応件数÷総着信数×100=応答率(%)
稼働率との違い:稼働率は広く顧客対応時間の割合を表すのに対し、応答率は「どれだけ電話を取れたか」を表し、観点が異なります。稼働率が高かったとしても、着信件数が多い、人員が足りないなどが原因で応答率が低下することがあります。
占有率とは?
占有率とは、オペレーターの稼働時間のうち、実際に顧客対応に当たっていた時間です。一般的には顧客応対時間のうち、待機時間を除く時間とします。顧客対応時間のうち、オペレーターが実際に顧客対応をしていた割合がわかります。
(通話時間+後処理時間+保留時間)÷(通話時間+後処理時間+保留時間+待機時間)×100=占有率(%)
稼働率との違い:稼働率には待機時間を含みますが占有率は待機時間を含まず、純粋に直接的に顧客対応をしていた時間がわかります。
稼働率を見る際には応答率も占有率も合わせて見ることで、より正確な状態を把握できます。
コールセンターの稼働率の課題
一般的に、コールセンターの適正な稼働率は80~85%といわれています。
コールセンターの稼働率は、高すぎても低すぎても問題です。それぞれ次のような課題が生じます。
稼働率が高すぎるときの課題
対応が必要な目安:稼働率90%以上
・オペレーターが常時対応に追われ、心身ともに消耗する
・応対品質低下による顧客満足度の低下
・ストレス過多
・離職率・欠勤率上昇
・応対品質の低下
稼働率が低すぎるときの課題
対応が必要な目安:稼働率70%未満
・着信数に対してオペレーター数が多いため非効率
・人件費の無駄が発生している恐れ
・勤務時間が長すぎる可能性
コールセンターの稼働率を適正にするポイント
稼働率は高すぎても低すぎても生産性低下を招き、オペレーターにとってのデメリットも多くあります。そこでマネジメント層がコールセンターの稼働率を徹底して管理することが大切です。適正値である80~85%を維持するための管理のポイントをご紹介します。
オペレーターのステータスをこまめに管理する
まず重要なのは、稼働率を厳密に数値化し、管理することです。そのためには、オペレーターのステータスを管理することが求められます。
オペレーターのステータス一覧
・通話中
・着信中
・待機中
・後処理作業中
・離席中
・研修中
・休憩中
・未稼働
これらのデータについて全オペレーター分を集計し、現状把握を行います。もしこの時点で「後処理作業中」が長すぎるなどの問題が見つかったら、改善することが可能です。
適切な人員リソース調整
オペレーターの人員調整は稼働率に直結するため、常にコントロール・見直しの意識を持つことが大切です。オペレーターが多いほど対応力が上がり、稼働率と応答率向上につながる一方、多すぎると稼働率が適正でなくなることもあります。オペレーターが少なすぎれば対応力が下がり、応答率が低下します。稼働率80~85%を維持できる最適ラインを見つけることが大切です。
生産時間と非生産時間のバランスを保つ
休憩時間などの非生産時間の割合が高い状態を放置することは、稼働率を下げる原因となります。一方で、非生産時間がほとんどない場合、オペレーターのストレスが高まるため、問題があります。生産時間と非生産時間のバランスを適切に保つことが大切です。
| 生産時間 | 通話中、着信中、待機中、後処理作業中 |
|---|---|
| 非生産時間 | 離席中、研修中、休憩中、未稼働 |
非生産時間が極端に多い場合は、研修や面談、オペレーター同士の交流、報告・連絡MTGなどに充てるのも有効です。
面談などオペレーターとのコミュニケーション
稼働率が高い場合などは、特にオペレーターのストレスが高い状態にあります。またクレームが多発している場合なども含めて、オペレーターのメンタルケアを重視することが大切です。
具体的には、日々、オペレーターの様子を観察する、日常的にコミュニケーションを頻繁にとるようにする、1対1での面談を定期開催するなどが考えられます。
システムの活用
コールセンターの稼働率を適正に管理し、業務効率を上げるために重要なのが、システムの導入です。下記のようなシステムを利用することで、稼働率の適正化にもつながります。
| PBX(構内交換機) | 外線・内線を制御 |
|---|---|
| CTI | 応対実績の自動集計、自動音声応答システム、着信自動振り分けなど |
| CRM(顧客関係管理) | 顧客情報の参照・応対記録の入力管理・トークスクリプト管理など |
| FAQ・チャットボット | よくある質問の回答についてオペレーターが参照 |
このように、コールセンターの稼働率は、適正値を維持するためには、厳密なコントロールが求められます。適切な管理が難しい場合は、プロの支援を受けるのがおすすめです。
まとめ
コールセンターの稼働率は、高すぎても低すぎても生産性の低下を招きます。こまめな管理や適切なリソース調整、待機時間などのコントロールやオペレーターのケア、コールセンターシステムでの管理などさまざまなアプローチが求められます。
もし自社内で稼働率の調整が難しい、これからコールセンターを立ち上げるにあたって、稼働率のコントロールに自信がないといった場合は、コールセンター運用代行サービスを行っている日本トータルテレマーケティングにご相談ください。
貴社のコールセンターに最適な稼働率のコントロールを長年の豊富な実績と経験、高い分析力により、適正に行わせていただきます。
 こちらのコラムを読んだあなたへ
こちらのコラムを読んだあなたへ日本トータルテレマーケティングの
コンタクトセンター
サービス資料
こんな方におすすめ
- ・コールセンターサービスについて知りたい
- ・コールセンターの成功事例が知りたい
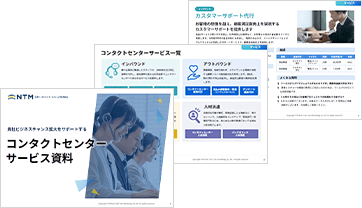
DL資料無料配布中!